日本史と聞くと大体どこから思い浮かべるでしょうか?
私はずっと日本史の始まりが曖昧で、覚えてるのは氷河期に北からマンモスが、南からナウマンゾウが陸伝いに日本にやってきて、それを追って人類が日本に到達した、マンモスとナウマンゾウがどっちがどっちから来たかは試験に出るので覚えておきましょうという事だけでした。
今回、ブログに書くにあたってその辺を整理しようと思い、わかりやすく日本列島の形成から書こうと思いました。
プレートテクニクスや中央構造線、フォッサマグナなどダイナミックで学んで楽しいことが多数ありましたが、ここでは流れを追うことを目的とし、極力細かい用語は省いて書いていきたいと思います。
約2500万年前-日本列島が徐々に大陸から離れ始める
地球は表面から順番に、地殻、マントル・外核・内核の順番で構成されています。地殻とマントルの最上部をプレートと呼びます。ここややこしいですね。私はプレートの下にマントルがあると思っていたのですが、実際は地殻とマントルの最上部をまとめてプレートと呼び、同じものに2つの呼び方があるイメージです。プレートは複数の岩盤によって構成されており、マントルの対流によって少しずつ動かされます。
プレートは大陸プレートと海洋プレートの2種類あり、海洋プレートは大陸プレートより重いので、双方が衝突すると海洋プレートが沈み込みます。沈み込んでいく過程で起きる摩擦や衝撃が、地上で地震に繋がります。また海洋プレートは水と一緒に大陸プレートの下に沈み込むので、一定のところまで水が入り込むと岩石の融点が下がり、岩石がマグマになって地上に上ります。それが地上で火山となり、地上での噴火や火山活動の原因になります。
これらのプレートの動きによってもたらされる地震や噴火などの動きを地殻変動と呼びます。
約2500万年前、日本列島はユーラシア大陸の東側の一部でした。
プレートによる地殻変動がおこり、ユーラシア大陸から少しずつ現在の日本列島になる陸地が引き裂かれました。最初は棒状に亀裂が入り、その後大陸の西南側が時計回りに、東北側は反時計回りに引き裂かれ、中央部が裂ける形で観音開きに陸地が動いていきました。そこに海水が流入し、海水が湖になり広がっていき、徐々に陸地が大陸から離れていきました。
離れていった陸地は太平洋プレートが運んでくる様々な堆積物をくっつけ、またプレート衝突によって地形が盛り上がり、造山帯が形成されていきます。
長い時間をかけ少しずつ今の日本列島が作られていき、今の形になったのはおおよそ2万年前のことでした。
約260万年前-旧石器時代が始まる
地球が頑張って日本列島を形成している間、人類は約260万年前に旧石器時代にはいります。
旧石器時代は前期・中期・後期に区分けされ、それぞれ後期が約260万年前 – 約30万年前、中期が30万年前 – 約3万年前、後期が約3万年前 – 約1万年前となっています。
日本では後期の旧石器時代の遺跡が多数発見されており、前期については発見されておらず、中期は少し発見されているが検証中、といった感じです。
人類が日本に到達したのはおおよそ4万年前ではないか、言われています。
約4万年前-人類が日本に到達
人類はアフリカで誕生し、様々な人類種へと進化・絶滅を繰り返しながら、およそ4万5千年前にオーストラリア大陸に到達しました。話は逸れますが、ホモサピエンスがオーストラリア大陸に到達したことは、アポロ11号が月に到達したのと同じくらいの快挙だそうです。人類が海で生きる為に必要な身体的な機能を必要とせず、自分たちの知恵で航海し、大陸に到達したからです。といっても月面着陸が一時期散々テレビで疑われたように、その頃の人類がオーストラリアにどうやって辿り着くことが出来たのか、まだはっきりとわかったわけではありませんが。
そんな人類が日本大陸に進出したのは約4万年前くらいだろうと言われています。日本の形が大体出来てきたくらいかなあというところでしょうか。地球はおおよそ1万年前まで、すごく寒い時期とそんなに寒くない時期を繰り返し、今より海水面もずっと低い状態でした。日本と大陸が地続きになっていた時もあると考えられ、人類もそのタイミングで日本に上陸したという説が通説でした。しかし最近では凄い寒い時期でも大陸から列島は地続きではなく、オーストラリア大陸に渡ったように海を航海したんじゃないかとも言われています。ルートは様々あり、大陸から対馬を中継して九州に上陸するルートと、台湾・琉球列島を辿って上陸するルート、またサハリンを南下して北海道に上陸するルートなど、色々なルートで日本にやってきたと考えられています。冒頭でも記述した北からマンモス、南からナウマンゾウを追ってきたというのはこの時代ですね。ちなみにナウマンゾウというのは日本の地質を研究して中央構造線やフォッサマグナを発見したナウマン博士からきてるそうです。
約2万年前-現在の日本列島の原型ができる
約2万年前、日本列島の原型が出来ますが、まだ今の日本列島とは違うところがあります。まだ氷河期が終わっておらず、海水面が今よりも低いので、今よりずっと大陸との距離が近いです。氷河期が終わり、海水面が上昇していくと、大陸との距離が広がり現在の日本が完成します。氷河期が終わってから海水面の上昇が終了するのも何千年かかかりますが、氷河期が終わった時点から縄文時代が始まります。おおよそ一万六千年前です。旧石器時代があるんだから新石器時代はないのか、とふと思ったりしますが、石器時代は旧石器時代、中石器時代、新石器時代と分けられ、世界的には青銅器を扱うまでの時代を指すそうです。それぞれの区分は世界の地域によって異なり、日本の中・新石器時代と縄文時代は重なっています。厳密に定義すれば若干のずれはありますが、おおよそ旧石器時代のあとは縄文時代と考えていいかと思います。
まとめ
約2500万年前に地殻変動によって大陸から日本列島が分離し始め、大体2万年前に今の日本列島の原型が出来、人類は旧石器時代で、約4万年前には日本に上陸していました。約1万6000年前に氷河期がおわり、縄文時代が始まります。ざっくり言うとこんな感じですね。次回は縄文時代に起こったこと、また当時の文化について書いていきたいと思います。

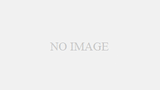
コメント